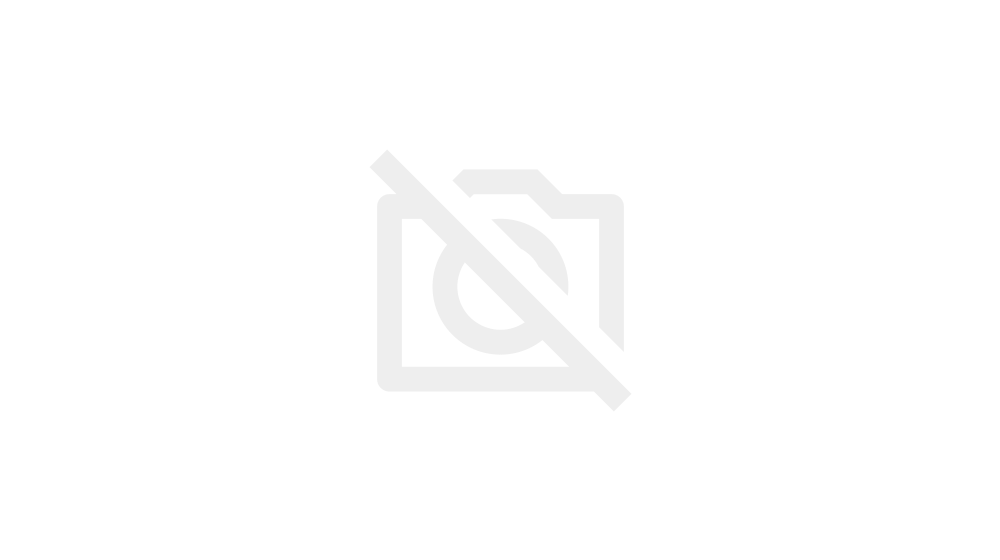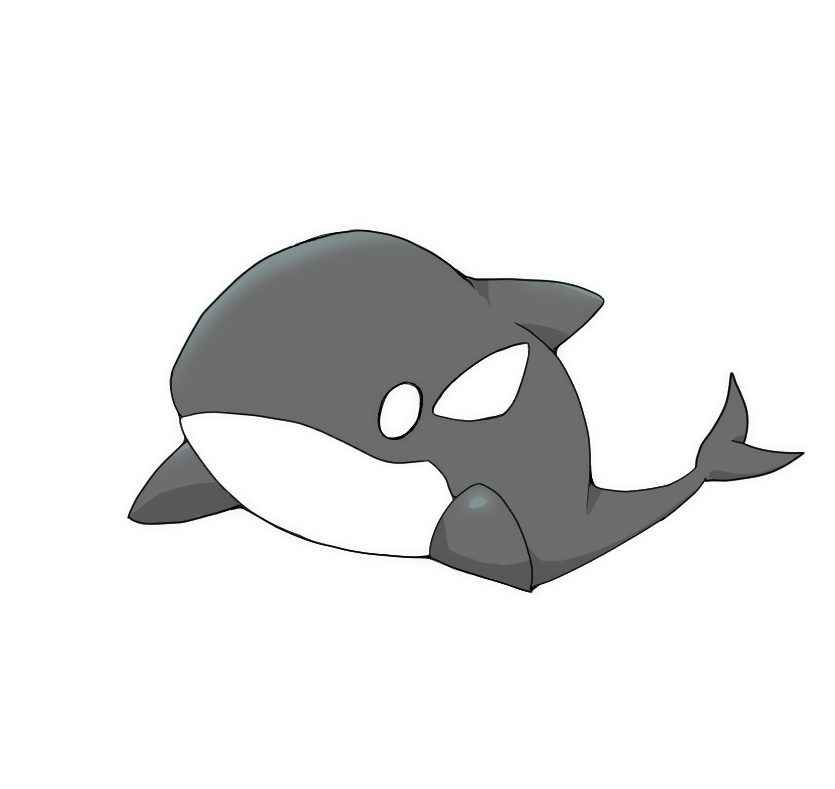個展の最終日の夜。
閉館間近の美術館に、涼は訪れていた。流石に人気はなく、殺風景だ。
誰もいない広い美術館に、自分のこれまでの作品が並べられている。
まるで今の自分のようだと苦笑いしながら「果たしてこれで採算がとれるのだろうか」と、今まで尽くしてくれたマネージャーの心配をした。
カツカツカツ。
誰も居ない美術館には、自分の足音しかしない。
タッタッタッ。
はずだったのだが。
「おや、若い足音が聞こえると思ったら」
振り返ると、そこには制服を着た女子高生が立っていた。その女子高生は涼と目が合うと、何か言葉を発しようとして、咳き込んだ。
どうやら長い距離を走ってきたようだ。
「あ、あの、私は」
「いいよ。わかる。みゅうみゅうだろう?」
「はいっ! ……えっと、羽月美優です」
そう嬉しそうに答えた。
「ここに来たってことはもう知っていると思うけど。石丸涼だ。画家のようなことをやっている。よろしく」
「よ、よろしくお願いします!」
「で、どうやって私のことを調べたの?」
「それは……」
ゲームとは違い、実際に見たハゼルこと石丸涼に圧を感じたのか、美優は少し怖がっているようだった。
「おいおいそう怯えるなよみゅうみゅう。怒ってるんじゃない。感心しているんだ」
「えっと……友達のギルティアって子が、ハゼルさんに見覚えがあるって」
美優がずっと仲直りしたいと思っていた友人の一人、ギルティア。彼女は最近、知り合いとその話題で盛り上がったらしく、頭の片隅に引っかかっていたのだ。
そして、後はネットで個展の情報を調べて、ここまでやってきたという訳である。涼がここに顔を出すのは今日この瞬間が初めてだったので、奇跡のようなタイミングだったと言えるだろう。
「で、その時【石丸涼】の話をしていた知り合いっていうのが、【ヨハン】ってプレイヤーなんです。その人、涼さんの同級生だったって。もしかして涼さんの捜している哀川圭って――」
興奮気味にまくし立てる美優の言葉を涼は手で遮った。
「知ってる」
あの日。美優が友人と仲直りしたあの日。すれ違った。その瞬間に全て気が付いた。
「会って行かないんですか?」
「会わないよ」
「な、何故ですか」
「確かに私は哀川圭を捜していた。けど別に会うために捜していたわけじゃない」
自分の画家としての人生が行き詰まったあの時。
ふと、昔の友人との思い出が蘇った。
無理矢理大人になろうとしていた彼女は、大丈夫だろうかと。
遠くから一目見られればそれで良かった。確かめられれば、それでよかった。
そして、涼は見た。
親友は、出会った日と変わらない、ひまわりのような笑顔をしていた。
「私が画家になったのはな。とある女を笑わせたかったんだ。心の底から、子供みたいに笑って欲しかったんだ。最近思い出した。初心ってヤツさ」
友人の笑顔を取り戻したい。自分以外の絵ではなく、自分の絵で。そんな初心は、流れていく忙しい日々の中で少しずつ薄れ、消えてしまっていた。
「けど、その役目は誰かが代わりに引き受けてくれたらしい。私はさ。多分アイツのことが心配だったんだと思う」
けれどもう大丈夫。
あの日、あの夏の日。かつて少女たちが夢見た場所で、哀川圭は幸せそうに笑っていた。
「それがさ。凄い嬉しいんだ」
涼のその顔を見て、美優は何か言いたそうに口をぱくぱくさせていた。
「それじゃ、ハゼルさんは……」
そんな言葉を言おうとして。
だが、それを飲み込んだ。
その時。
閉館を告げる音楽が鳴った。
「さ、仕舞いだみゆみゆ。家には自分で帰れるか? お姉さんが送っていってやろうか?」
「大丈夫です。ここから電車で30分くらいなんで……」
それ以降、何も会話をせず、美術館を後にした。
そして。
別れ際、美優が振り返った。
「哀川さんに会わない……それはもう何も言いません。本当は言いたいけど、言いません」
「おいおい怖いな。さてはみゆみゆ、結構根に持つタイプだな?」
「真面目に聞いて」
「あ、はい……」
その美優の迫力に思わず怯む涼。
「涼さん。貴方のもう一人の相棒、イヌコロにお別れは言いましたか?」
「そういや……」
言ってなかったなと思い出す涼。
「海外からじゃ日本サーバにはログインできませんから……ちゃんとお別れしてあげてください」
「んんん……わかった。わかったよ」
涼は少し面倒に感じながらも、美優と別れた後、自分の滞在するホテルへと戻った。
-

-
12 離れていても
「召喚獣召喚――イヌコロ!!」 「わふ!」 その夜、日付が変わる頃。 ログインしたハゼルは第一層はじまりの街に向かうと、周囲に誰もいないことを確認してから召喚獣を召喚する。 幾何学的な魔法陣から、 ...
続きを見る